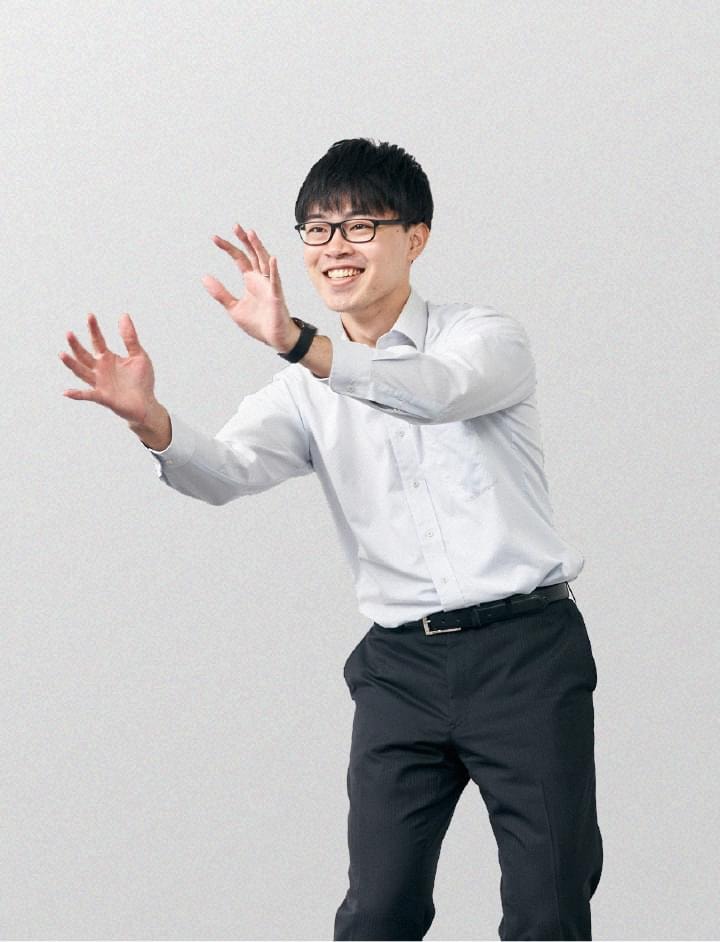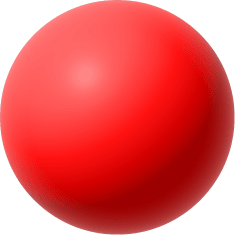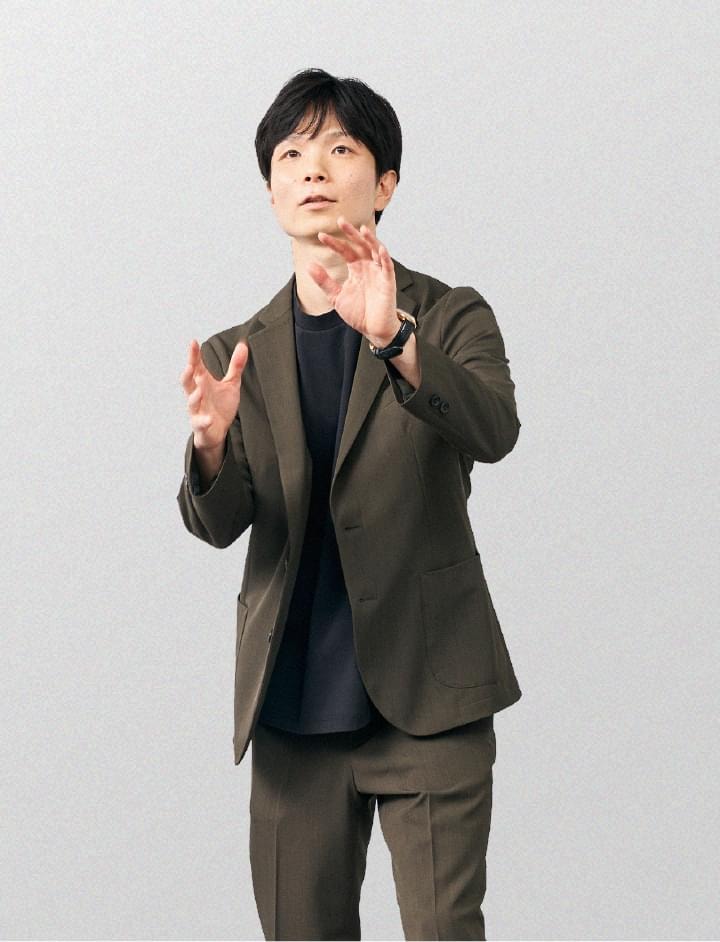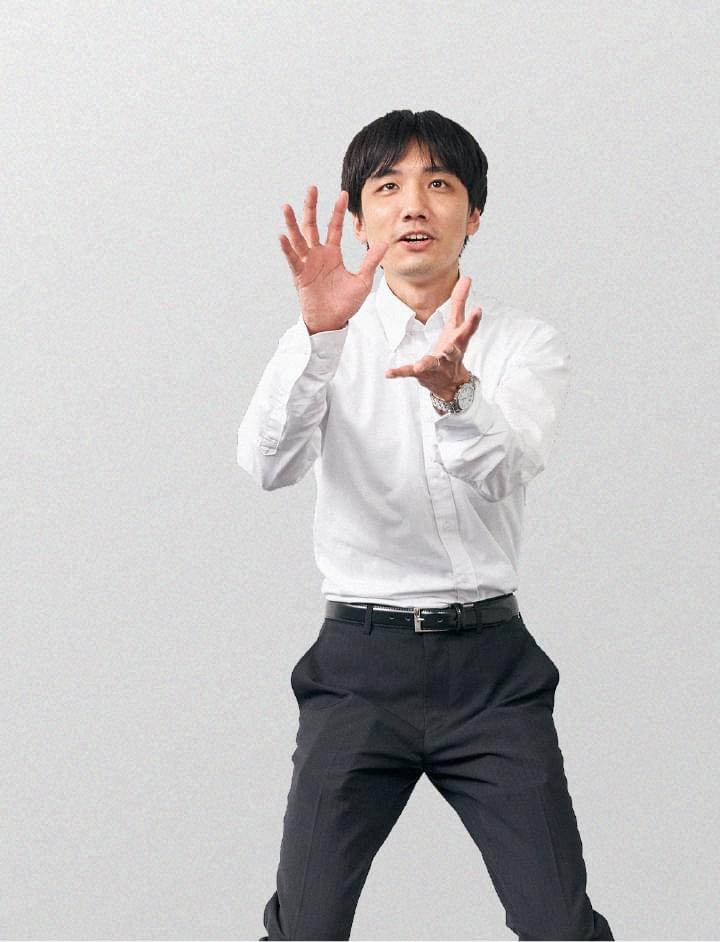赤文字だらけの
要件定義書。
文系出身の私にとって、システムエンジニアの仕事は挑戦の連続でした。入社して最初に担当したのは、日本マスタートラスト信託銀行の基幹業務に関わるシステム改修。お客様に送る帳票の出力仕様を少し変更するだけの小規模な案件でした。しかし、IT素人の私は些細な業務もままならず、失敗ばかり。今でも忘れられないのは、初めて自分で書いた要件定義書が、先輩の添削で赤文字だらけで戻ってきたこと。なぜこんなに出来ないのかと、不甲斐なさで本当に悔しかったのを覚えています。けれど、当時の自分に伝えたいのは、月並みですが、焦らなくて大丈夫、ということ。設計、実装、テスト。システムの開発には、どのプロジェクトでも共通する、普遍的なサイクルがあります。そのサイクルを自分なりの工夫を持って回していけたら、着実に力は伸びていく。そして、この会社には、同じように未経験からスタートした先輩たちがたくさんいて、優しくサポートしてくれます。私自身、社内の勉強会や日々の先輩との会話を通じて、徐々に技術を磨いていくことができました。
1000名の働き方を
変えるために。
今、私が担当しているのは、日本マスタートラスト信託銀行の業務フローに関わるシステムの保守。従来、紙とハンコで行われていた契約書のやり取りを、電子上で完結できるシステムです。改修内容は、書類をクリックしてから、表示されるまでの時間を2秒短縮するというもの。軽微な変更のように思われるかもしれませんが、このシステムは、日本マスタートラスト信託銀行の全社員、約1000名が日常的に活用する大規模なシステム。影響は広範囲に及びます。さらに、部署によって使用するパソコンの性能が異なるため、それを考慮した仕様を決める必要があったりと、要件定義一つとっても、苦労は絶えません。例えば、プロジェクトに関わるメンバーの会社や部署が異なると、普段当たり前に使っている用語さえすれ違いの原因となります。「リリース日」という用語の意味は、サーバーにテストアップする日か、実際に改修後のシステムを使える日か。些細なコミュニケーションにも気を配り、説明の順番や図の見せ方にまでこだわる。そうして何度も打ち合わせを重ね、約1年かけて全ての改修を完了することができました。大変でしたが、1000名の働き方をより良く変えるという使命感が、常に私のモチベーションになっていました。
歴代の想いがこもった
プロジェクト。
私が担当したのは保守業務ですが、部内にはかつてこのシステムをゼロから開発した上司がいます。改修が完了した日、その上司に声を掛けられました。「よくやった」、たった一言でしたが、その一言の重みを考えると、気が引き締まりました。当時の技術開発では、一体どれほどの試練を乗り越えたのだろう。社内外の関係者に掛け合って、何度もトライアンドエラーを繰り返して。同じシステムに関わったからこそ、その熱量が身に染みて感じられました。
一つひとつのシステムは、歴代のエンジニアがつくり、守り抜いてきたもの。私たちには、それを引き継いでいく責任があります。そして、どのような時代も盤石なシステムを構築することが、信託銀行とお客様の信頼関係にも繋がるはずです。エンジニアが担う日々の業務は、とても地道なもの。でも、その小さな一歩の積み重ねが、信託銀行の歴史をつくる。私はそう信じています。
休日の過ごし方
海外ドラマをよく鑑賞しています。BGMの音楽や物語の舞台設定など、海外ならではのカルチャーを味わえるのが面白いですね。それ以外だと、妻と一緒にショッピングをすることも多いです。洋服を見たり、インテリアを物色したり。最近は、色違いでお揃いの靴を買いました。